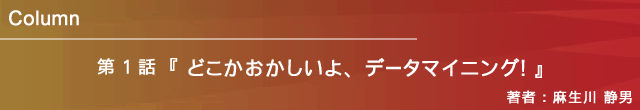
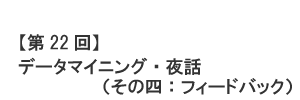
【第28回】データマイニング・夜話
(その十:子供の頃わくわくした事)
コラムTOPへ戻る
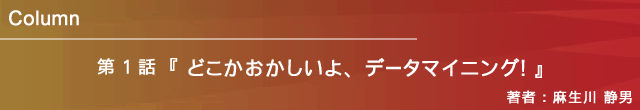
|
|
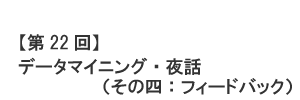 |
|
【第28回】データマイニング・夜話 (その十:子供の頃わくわくした事) コラムTOPへ戻る |
|
| 私が大学に入学したのは、オイルショックという歴史的事件があった年ですので、すでに30年も前になります。 当時京都に下宿していましたが、オイルショックで下宿代は契約期間の途中から値上げされ、それが発端で契約のごたごたがあり、結局1年で下宿は追い出される羽目になりました。そこから下宿を転々とし、途中にドイツ留学などもあり、結局6年間に下宿を都合5回変わることになったのでした。 その中には、きわめて居心地のいい部屋もありました。銀閣寺の近くの下宿は、窓の下には比叡山からの清水が流れ、近くの林からは、今で言う森林浴のマイナスイオンが毎朝漂い出ていました。また歩いて数分の所に、有名な哲学の道がありました。琵琶湖から引かれた水量豊富な疎水が古木の並木道の情緒をいっそう引き立てていました。このようにこの下宿はいい点が多かったのですが、難点と言えば西日がまともに入ることでした。夏の夕方などはまるでサウナでした。 さてその下宿は私のような昭和30年生まれは一番の若造で、皆私より数歳上の人たちばかりでした。私の向かいの人は愉快で包容力ある人柄のため、部屋はハンドボール部のたまり場と化し、いろいろな人がしょっちゅう出入りしていました。その人はマージャンが大好きで、本当は厳禁のはずのマージャンを消音と称して毛布を敷いてするのですが、夜中まで続くガチャガチャという音には一度ならず悩まされたものでした。しかし、私もその内呼び込まれ、とうとうマージャン仲間にされてしまいました。九蓮宝燈(チューレンポート)という一生に一回あるかないかの大役満をあがることになったのもこの部屋でした。巷の迷信では、この役を上がった人は、不運に見舞われるということですが、私もこの数日後に横断歩道で危うく、車に轢かれそうになりました。隣を歩いていた下宿の別の先輩に腕をひっぱられ、辛くも事故を免れることができたのでした。その生粋の江戸っ子の先輩は、タバコの吸いすぎのせいでしょうか、肺がんで先年惜しくも50過ぎで早逝してしまいました。 皆がこの愉快な人の部屋にくるのはマージャンだけではありません。もう一つの理由は挽き立てのコーヒーが飲めることでした。当時はまだコーヒーが高く、東京はどうだか知りませんが、京都などでは、コーヒーを一杯注文するだけで喫茶店に終日居すわることも可能な時代だったのです。さて、当時一番の若輩であった私は、この部屋に行くと決まってコーヒー豆を挽く役目を押し付けられました。手回しのコーヒー挽き器で5〜6人分の豆を挽くのは結構時間がかかったものです。現在では、モーターのスイッチを押すと数秒で豆が挽けますが当時はそのような利器は学生には無縁のものだったのです。 手回しコーヒー豆挽き器で挽いたコーヒーを飲んでみるとおいしい時とまずい(苦い、みずっぽい)時があるのを何度か経験しました。コーヒーのおいしさには、粉の粒度が大きく関係しています。手回しでは説明しにくいので、モーター式について説明しますと、モーターを回す時間が長いと、粉が細かくなり、苦くなります。逆に短か過ぎると、粒が粗くなり水っぽくなります。つまりモーターを回すのに最適な時間があるわけです。 QC(Quality Control:品質管理)の観点から、おいしいコーヒーを飲むにはコーヒー豆をどう挽けばいいのか、モーター式の場合について考えてみましょう。 QCでは必ず計測データが必要です。それも条件を計画的に変えて、最適な値(今回の場合はおいしいコーヒー)を見つけることになります。具体的には、ある一定の量のコーヒー豆をモーターで規定時 間回して出来た粉からコーヒーを入れて実際の味を何人かの人においしいかどうかを判断してもらいます。モーターを回す時間を少しづつ変えてこの実験を繰り返します。 図1:一番おいしいコーヒー豆を挽く時間を決める 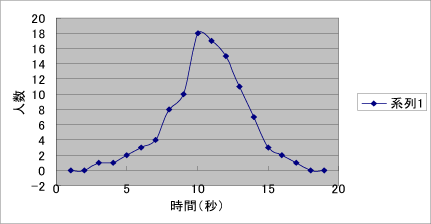 例えば上図のような実験データを得られたとしましょう。グラフの真ん中あたり、つまり挽く時間が10秒近辺のときの粉がおいしいと感じる人が一番多いことから、最適な時間はこのあたりであると分かります。この結果コーヒー豆を挽く時にはモーターを10秒回しなさいとマニュアル化することで、いつも確実においしいコーヒーが飲めるようになるでしょうか? 事態はそう簡単ではなさそうです。というのはコーヒー豆というのは、産地や種類もさることながら、湿気や温度によって堅さが変わります。おいしいコーヒーを入れるにはそのような状況に対応して挽き方、あるいは挽く時間を調整する必要があります。そのためには、数多くの状況に応じて数多く実験し、そこから最適な時間を求める必要があります。このような方法論は実験計画法と呼ばれています。 一方手回しの場合のコーヒー挽き方を考えてみましょう。同じ量のコーヒー豆でも、力の入れ具合が異なれば、当然粉の粗さも異なります。また湿気で手に伝わる反応も異なります。回す回数や回す時間というような計量的な指標は当てにはなりません。つまり計量化できる指標ではなく、手に感じる力という極めてアナログ的な感覚を指標としなければなりません。結局この方式では各人が経験を積み重ねていくことで最適な力の入れ方を『会得』する必要があるのです。 この2つの手法を比較しますと、 表1:コーヒー豆を挽く2つの方式の比較
この二つの方式の決定的な違いは、次の二点にあります。 1.フィードバックのあり/なし 2.指標がデジタル量(秒数)/アナログ量(手に感じる力) モーター方式では、予め決めた時間だけモーターを回します。一方、手回し方式では、湿気や豆の堅さによって力の入れ方を自在に変えることで、最適な粒度の粉にすることが出来ます。時間はかかっても最終的には、最高の味を引き出す秘訣はアナログ的に力の大きさを微妙に調整できる手のフィードバック機構にあったのでした。 この観点から日本の伝統工芸を考えてみますと、ほとんどの場合後者の(手回し)方式であること分かります。例えば料理の場合なども、欧米では、調味料の量はカップ何杯とか、スプーン1/4、塩何グラム、などと事細かく記述しますが、和風の味付けは、塩・みりん少々などというように曖昧模糊とした表現になっています。従って最適な量の決定は必ず味見(フィードバック)してから決める必要があります。(もっとも西洋料理でも一流のコックはやはり味見をしているみたいですが。。) このような日本と西洋の差は伝統工芸の分野だけでなく、私たちの行動様式に根深く食い込んでいます。端的に言いますと日本人にはファーストフードのチェーン店などが採用している、店員の行動をマニュアルで縛る方式はあまり歓迎されません。日本人には、本来的に各人がそれぞれの状況に応じて臨機応変に対応する気質と能力が備わっているのです。しかるに、その貴重な長所を殺して、全てをマニュアル方式に変えることがベストプラクティスである、と勘違いしているところに現代日本の産業界の沈滞の一因があると私は感じます。 |
||||||||||||
|
続く... |
||||||||||||
|
△TOPへ Copyright © 2006 Zetta Technology Inc. All rights reserved.
|
||||||||||||